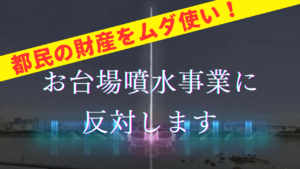はじめに
東京都がかつて自らが掲げた「合計特殊出生率2.07」という明確な少子化対策の目標数値が、現在の計画から削除されているのをご存知でしょうか。
令和元(2019)年12月に、東京都は2040年代に目指す東京の姿、ビジョンとその実現のため、2030年に向けて取り組むべき戦略を示した「未来の東京」戦略ビジョンを策定しました。
その中で、東京都は「少子化の課題に取り組む」として、以下の通り掲載しています。
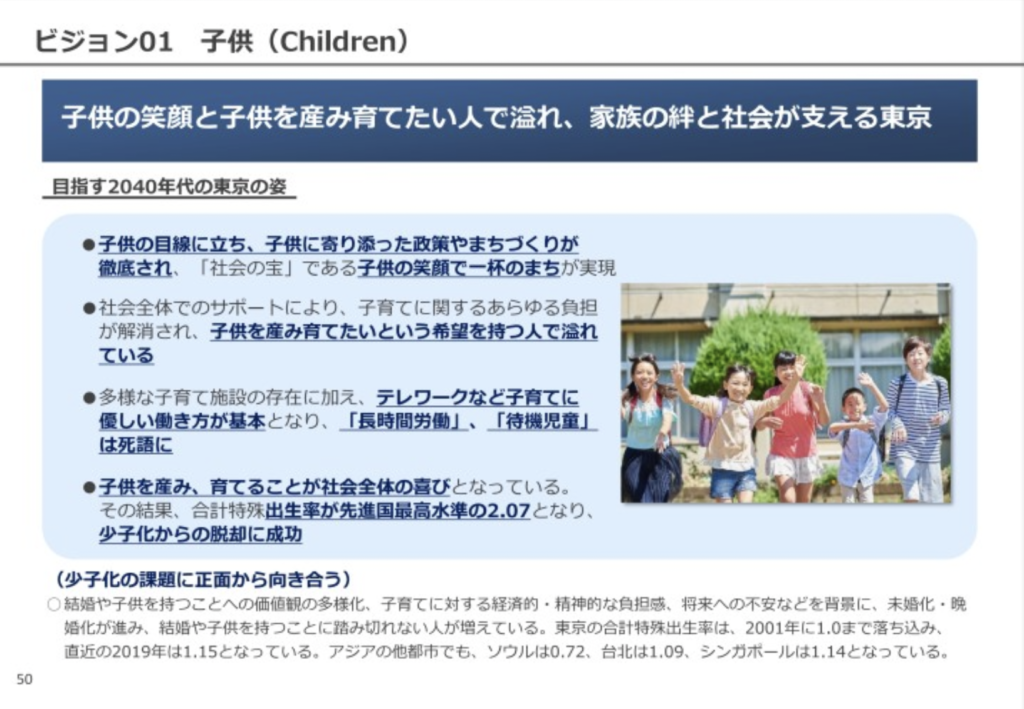
東京都の公式ホームページからは削除されていましたので、保存していた概要版を公開します。こちらでも合計特殊出生率2.07という数値が出ています。
しかし、この2.07という数値は、この「未来の東京」戦略ビジョン以降、どこにも見当たりません。
私はこの点について、3月14 日に行われた予算審査特別委員会にて、小池都知事に質疑を行いました。
本ブログでは、質疑の内容と、数値目標を消したことへの問題について解説します。
子育て支援における数値なきビジョンの問題点について
2019年に策定された「未来の東京」戦略ビジョンでは、東京都の人口が2025年にピークを迎え、本格的な人口減少時代に入ることを見据えた上で、合計特殊出生率2.07という数値を明記し、これを目指す強い意思が示されていました。これは単なる理想論ではなく、「子どもを持ちたいと願う個々人の想いを叶え、人口減少に歯止めをかける」という、都政の根幹に関わる重要な目標だったはずです。
ところが、2024年1月に公表された「2050東京戦略(案)」には、この数値目標は一切記載されていませんでした。
私は、なぜこの数値が削除されたのかについて、以下の通り質疑しました。東京都の答弁と併せて引用します。
令和7年予算特別委員会(第4号)(速報版) 本文 2025-03-14より抜粋
<さんのへ委員>
令和七年度当初予算において、一般会計の総額は、前年度比八・三%増の九兆一千五百八十億円と四年連続で過去最大を更新し、初めて九兆円台となりました。
小池都知事は、本当初予算を公表した定例記者会見において、少子化は社会の存立基盤を揺るがしている国家的な課題であり、都は、もはや一刻の猶予もないと述べられています。
実際に、都の少子化対策として令和七年度一般会計予算に盛り込まれた子育て費用の支援をはじめ、ライフステージをシームレスにサポートする子育てしやすい東京の実現に係る予算が一般会計全体の二割に当たる、約二兆円が各施策に計上されています。
過去の話になりますが、二〇一九年に、都は、二〇四〇年代に目指す東京の姿、ビジョンとその実現のため、二〇三〇年に向けて取り組むべき戦略を示した「未来の東京」戦略ビジョンを策定し、公表しました。
このとき、私は江東区議会議員に就任したばかりでしたが、この冊子を手に取って読んだことを鮮明に覚えております。
理由は二つありまして、その一つは、表紙の絵が、江東区立の小学校に通う子供が描いた絵で、「ちじょうがぜんぶこうえんになったまち」というタイトルで、車や電車が飛んでいたり地下に住む人がいるなど独創的な絵だったということ、もう一つは、東京都の人口は二〇二五年でピークを迎えた後に、本格的な人口減少時代に突入するということが明記されており、そのことに対する強い危機感を抱いたためです。
質疑に当たり、私の記憶が正しいか読み返してみましたが、しっかりと明記されていました。
さらに、東京都の人口は二〇二五年に一千四百十七万人でピークを迎えるとあり、この人口数値は、令和七年一月一日の時点の推計で一千四百十九万人で、かなり近い数字をいい当てていることも分かりました。
目指す二〇四〇年代の東京の姿という項目の中には、このように書かれていました。
子供を産み、育てることが社会全体の喜びとなっている。その結果、合計特殊出生率が先進国最高水準の二・〇七となり、少子化からの脱却に成功、また、我々は、次世代に幸せと希望に満ちた社会を引き継ぐため、強い危機感を持って、この問題に正面から向き合っていく。人口維持に必要な水準である合計特殊出生率二・〇七という数字は、子供を持ちたいという個々人の願いをかなえるとともに、人口減少に歯止めをかける決意を表すものであるとありました。
一方で、今年一月に概要が公表された二〇五〇東京戦略(案)では、都として強い決意表明があった合計特殊出生率二・〇七という数字はどこにも掲載されておりませんでした。
都としての長期計画から、この合計特殊出生率の目標を消した理由について、小池都知事に伺います。
小池都知事に伺ったものの、答弁拒否され、政策企画局長からは以下の答弁がありました。
<政策企画局長>
「未来の東京」戦略で掲げました百六十四の政策目標の中に、お尋ねの合計特殊出生率については含めておりません。
一方で、ご質問のように、合計特殊出生率二・〇七は、少子化の課題に向き合う姿勢としてお示ししたものでございます。
少子化の要因は複合的であり、新たな二〇五〇東京戦略でも、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援に加え、教育、住宅、就労や職場環境などの幅広い分野での対策が必要であるとの認識の下、婚姻率、出生数、有配偶出生率、男性の育業取得率など様々な指標に着目しながら、取組を進めていくこととしております。
引き続き、望む人が安心して子供を産み育て、子育ての喜びを実感できる東京の実現に向けて政策を展開してまいります。
つまり、東京都として合計特殊出生率2.07は、姿勢として示しただけであって、今後は婚姻率や有配偶出生率、男性の育業取得率など多様な指標を活用する、という方針のようでした。
しかし、これは本来のビジョンにあった「具体的な到達点を示す」という意義を放棄したに等しいと言わざるを得ません。
危機的な少子化に瀕する日本において、議員からすると子育て政策は疑義を呈しにくいものであり、謂わば金科玉条ともいえるものです。
東京都の子育て政策の効果を測る目標に、多様な指標を用い始めると、金科玉条たる子育て政策にかこつけて、曖昧な目標・疑わしい効果の事業を、特定の事業者に委託させたり中抜きさせられるようになってしまいます。
例えば、都知事選直前に突如として発表し1,200億円もの予算を計上した018サポートは、あまりにも突然発表されたことで、都の事務的な準備が不十分なまま推し進められたことで、誤送付・誤配が相次ぎ、生活保護世帯への未支給や、子供1万人分の過支給等、ミスが大量に発生し、これに対応するために、多くの都民の税金が浪費されてしまいました。
かつて小池都知事は、「都政はエピソードベース(経験則)からエビデンスベース(客観的データ)へと転換すべきだ」と公言されました。
(参照:小池知事「知事の部屋」/記者会見(平成29年7月21日)https://www.metro.tokyo.lg.jp/governor/kishakaiken/2017/7/21)
これは私も強く賛同するもので、子育て政策に限らず、公共政策は、具体的な数値をもって立案・評価されるべきです。
目標値のない政策は、言わばゴールのないマラソンです。どれほど走っても、その成果を測る術がありません。
メンっ!と総括
東京都は令和7年度予算で、子育て関連事業に約2兆円もの予算を計上しました。これは重要な投資であり、評価できる面もあると考えます。
しかしながら、「成果の物差し」たる数値を自ら放棄してしまえば、それは善意と雰囲気に頼った“エピソードベース”の政策運営に逆戻りしてしまいます。
都政が今後も「少子化対策」を真剣に推し進めるのであれば、説明責任から逃げず、数値目標を曖昧にせずに都民と共有してほしいのです。
昨年、東京都が全国(都道府県)の中で最も低い合計特殊出生率(0.99)となった事が報道されました。合計特殊出生率は、若い女性が流入する都市部において特に低くなる傾向があるとされているため、東京都として、合計特殊出生率が低いことを、行政側としても、問題視しなくなってしまったようにも感じます。
しかし、だからこそ、その東京都が合計特殊出生率を上げる為に効果的な施策展開を追及し続ける必要があると考えます。
そしてその取り組みの効果を測るのは、数値というエビデンスに他なりません。
私は子育て支援に係る所得制限の撤廃を国や東京都に訴え、児童手当などにおいて所得制限の撤廃が実現しました。引き続き、障害児(者)支援に係る所得制限の撤廃に取り組んでいます。
私はこれからも、当事者である都民の声に真に応える政策の実現を追求してまいります。同時に、未来世代に責任をもち、私たちの子供たちにつけを回すようなバラマキ政策を許さない姿勢で、エビデンスベースの都政運営の実現を求めてまいります。
さんのへ あや