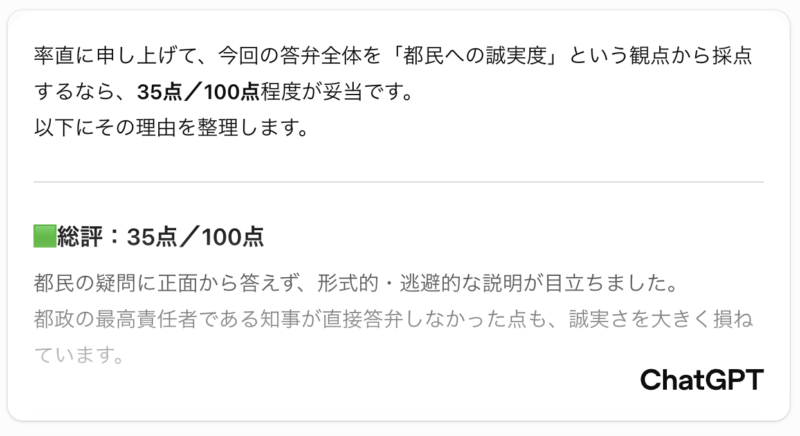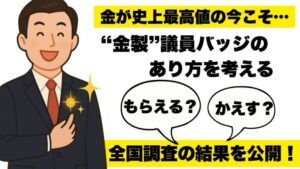はじめに

2025年月10月2日(木)、都議就任後3回目となる一般質問を実施して参りました。
この日は、傍聴席が満席になり、インターネット中継も閲覧できない人が出るなど、多くの方にご注目いただいていたため、毎回恒例となった「小池都知事からの答弁拒否」と「都庁幹部からの不誠実な回答」が多くの方の耳目に触れることとなり、大きな反響を巻き起こしました。
前回に引き続き、より多くの方に理不尽な都の姿勢を知っていただくために、質問及び回答の全文を公開します。
また、読みやすさを追及するため、一問一答形式にしておりますのでご了承下さい。
なお、当日のインターネット中継動画の録画は、以下のリンクからご覧頂けますので併せてご覧ください▼
https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/live/video/251002.html?seek=21114
⑴エジプト政府との合意について
(さんのへ あや)
はじめに、エジプト政府との合意について伺います。都は8月19日付けで「エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書」を締結しました。
質問①都は多くの国や都市と交流や協力を進めてきましたが、自治体が特定の国を対象に、雇用促進に積極的に関与する合意を、外国政府と結んだ前例はありますか。合意書第2条の1では、都がエジプト人労働者に対してのみ国内での仕事を確保し情報提供をする特別扱いになっています。この経緯と意図について、小池都知事に説明を求めます。
質問②また、合意書第3条の2では、予算を伴うことを想定していますが、どの項目に、どの程度の予算額を想定していますか。
更に、質問③特定国への支援は地方財政法や外国為替管理法等関係法令に抵触しないか、見解を伺います。都は他国と合意書を結んできましたが、雇用に関するものは今回が初めてです。そして、都は理由として友好都市関係や知事の訪問を挙げています。しかし、なぜ雇用の合意をエジプトとのみ結ぶのか、根拠は依然不明確です。不安を抱く都民が声をあげれば「誤情報」「排外主義」と決めつける姿勢こそ、都民排外主義の誹りを免れないのではないでしょうか。
(産業労働局長)
2点のご質問にお答えいたします。
エジプト側との合意についてでございます。他自治体において、海外の都市や国との雇用分野に関する合意書等の締結は行われております。都は、これまでもエジプトと様々な交流をしておりまして、友好関係の発展について意見交換を行い、実務的な協議を重ねた結果、この度、雇用のほか複数の分野の合意書締結に至ったものであります。次に、合意書第3条第2項についてでございます。この規定では、予算具体的なプロジェクト契約及びスケジュールを含む実施の詳細は、両当事者が別途かつ相互に合意して策定するものとするとしております。
今回の合意内容は、エジプト側で実施されます日本での雇用に必要なスキル、基準の研修等について、都は助言や情報提供などを行うものであります。今後必要があれば規定に基づき対応いたします。
(政策企画局長)
合意書の締結についてのご質問にお答えします。
都が海外の都市や政府機関等と結ぶ合意書は、相手側への支援だけではなく、人的交流や情報交換等を通じて、特定分野の協力関係を促進することを目的としております。本合意書は法令に抵触するものではございません。
以下、再質問部分(25秒)
(さんのへ あや)
他自治体が諸外国と雇用支援を結んだ事例は、いずれも明確な産業ニーズが背景にあります。歴代都知事初となる外国との雇用促進合意を結ばれた都知事に、その背景・経緯、数ある国の中でなぜエジプトなのかを再度伺います。知事は都民に自ら説明できないような合意を結んだのですか?お答えください。
(産業労働局長)
質問にお答えいたします。
先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
⑵火葬場について
(さんのへ あや)
次に、火葬場についてです。
都内の火葬場の7割超を運営する東京博善が火葬料金を再び値上げします。さらに、都知事特別許可で設置された代々幡斎場や堀之内斎場では、無申告の増改築疑義があります。
質問④都はこれら施設の増改築をどう把握し監督しているのか、変更は正式に許可したのか、時系列でご説明ください。
質問⑤東京博善が運営する全施設についても、変更申請や許可手続きは適正に行われているのか伺います。
知事は代表質問で「区市町村と連携する」「実態調査する」と答弁しましたが、東京博善が2020年に外資系子会社となる以前から、区長会をはじめ関係者は、都に対して広域的対応を求めていました。にもかかわらず、都は”所管外”と一蹴し、その結果、外資支配、相次ぐ値上げを招きました。想定可能な事態にも、都は手立てを講じませんでした。増改築は固定資産税にも影響します。特定行政庁移管時の引き継ぎがきちんと行われたのか、これまでの対応の遅れを踏まえ、今後は都が主体性を持ち責務を果たすべきです。
(保健医療局長)2点のご質問にお答えいたします。はじめに、火葬場の指導監督についてでございますが、火葬場の設置や変更の許可は、御枚法に基づき、島嶼地域は都が、それ以外の区域は市町村が行っております。次に、火葬場の変更申請等についてでございますが、区部の火葬場に関しては、墓埋法に基づき、当該火葬場が所在する区が変更許可等を行っております。
⑶中央卸売市場の公益性について
(さんのへ あや)
次に、同じく重要な公共インフラである中央卸売市場の公益性についてです。
複数の市場関係者への聞き取り調査において、経営難等により外国資本の参入が進んでいる実態を確認しました。令和5年度の調査では、仲卸業者の45.5%が赤字経営であり、その状況は今もなお深刻です。現行の卸売市場法には、資本構成に関する直接的な規制や報告義務は定められておらず、独占禁止法は競争確保を目的とするもので、公設市場の公共的使命を、企業に課す仕組みは含まれていません。
質問⑥大規模災害やパンデミックによる流通途絶に備え、買い占めや国外転売で、都民・国民への食料供給が脅かされぬよう、食料品備蓄や都の指示に基づく供給義務を課す条例の改正を検討すべきと考えますが見解を伺います。条例改正が難しくとも、災害時協定等の締結や、法的拘束力のある予防措置の検討が必要と考えます。
性善説に基づいて運用されてきた法令の隙をついて、不透明な資本流入や支配が進み、市場の公正な競争と公益性が脅かされることになる前に、日本の首都東京の「食の安全保障」「食文化と伝統、ブランド」を守り、受け継ぐための予防措置として、質問⑦都として仲卸業者の資本関係を把握する新たな調査手法や情報開示の義務付けを検討すべきと考えますが見解を伺います。
(中央卸市場長)
2点のご質問にお答えいたします。
まず、有事における食料供給についてございますが、生鮮食料品の買占め等は、不公正な取引として、東京都中央卸し実施所条例で規制されてございます。また、発災時の生鮮食料品の確保につきましても、本条例のほか、災害対策基本法等の関係法令に基づきまして、既に必要な措置が定められていることから、条例改正が必要な状況とは考えてございません。
次に、指導業者の資本の調査等についてでございますが、東京都中央卸売市場条例では、取引参加者の資本関係を問わず、買占め等、不公正な取引を禁止するなど、生鮮食料品等の円滑な教育を確保するため必要な規制が既に設けられており、
市場業者の使用に係る新たな調査等が必要な状況とは考えてございません。
⑷補助金適正化条例について
(さんのへ あや)
最後に、補助金交付の透明性確保についてです。都では「補助金等交付規則」に基づき申請交付指導検査が行われていますが、補助金サーチ見える化ボードでは、概要のみで、支給先がわかりません。
質問⑨給付行政の透明性や説明責任の担保は不十分ではないか、知事の認識を伺います。
同様に規則を持つ北海道は、補助事業者名まで公表しています。都の補助金支出は、過去には1兆円を超え、一般歳出の約3割に達した年度もありました。不正受給の事例も後を絶たず、また外資を含む様々な事業者が公共事業に参入する中で、補助金の透明化と適正運用の徹底は税金を守る上で喫緊の課題です。補助金が公正に使われていることが都民に伝わるよう、透明性を高めるべきです。
そこで、質問⑩虚偽申請や不正受給について、国の補助金等適正化法にならい返還義務や刑事罰を設ける条例化、或いは第三者による監視機関「補助金Gメン」の設置など監視強化を検討すべきと考えますが、知事の所見を伺います。
以上で、再質問を留保し、自由を守る会 さんのへあやの質問を終わります。
(財務局長)
2点のご質問にお答えいたします。
まず、補助金についてでございますが、都はこれまでも補助対象や補助率、予算額などを都民が容易に検索できる「東京補助金サーチ見える化ボード」を公開しておりまして、補助金に関する透明性の確保とアカウンタビリティの充実を図っております。
次に、補助金の交付についてでございますが、都はこれまでも補助金に係る不正や違反があった場合には、補助金等交付規則等に基づき、返還命令を行うとともに、必要に応じて法的措置をとるなど、厳正に対処しております。また、地方自治法に基づき実施している監査委員による定例監査や財政援助団体等監査等を通じて、補助対象事業が補助金の目的に沿って適正に執行されているかなどを検証しております。
メンっ!と総括
今回の一般質問では、都政運営の根幹に関わる「説明責任」と「透明性」を問いました。
中でも、東京都がエジプト政府と締結した雇用促進に関する合意は、自治体として極めて異例の内容です。特定の国を対象に、都が主体的に雇用に関与することは、これまでの都市外交の枠を超えたものであり、その経緯や政策的根拠、法令上の整理を都民に明らかにする責務があります。
しかし答弁では、形式的な「助言・情報提供」という表現に終始し、都知事自身からの説明はありませんでした。都民の理解を得る上で最も重要な「なぜ今、なぜエジプトなのか」という問いは、なおも置き去りにされたままです。
火葬場問題や中央卸売市場への外資参入、補助金の適正化といった他のテーマも、共通して「都がどこまで実態を把握し、責任を持って監督できているのか」という構造的課題を浮き彫りにしました。
都政が巨大化・複雑化する中で、都民の信頼を支えるのは、制度でも仕組みでもなく、説明を尽くす姿勢そのものです。
今回の質疑は、単に政策の瑕疵を指摘するためのものではなく、都政の“見えない領域”を都民の目に可視化するための第一歩でした。
今後も、誤魔化しや印象操作に流されず、事実と論理に基づいた質疑を重ね、都政を「誰のためのものか」という原点に立ち返らせる責任を果たしてまいります。
追伸: 客観的な立場から、ChatGPTに東京都の回答を分析させ、点数を付けてもらったところ、100点満点中35点という結果でした。
さんのへあや